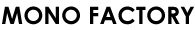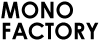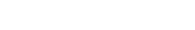Raw Materials : 陶芸に使われる原料
メモ。釉薬原料のまとめ。 特徴をまとめてみました。調合などのヒントに。
釉薬(器を彩る色)に使用されている原料を一部紹介します。ここでは、釉薬に使用されるものに限らす私が触れたことのある原料を中心にその原料名と特徴などを取り上げてみました。毒物もありますがアトリエで使用している食器用の釉薬は完全に融解し無毒化される範囲での添加量です。また、鉛など現在食器として使うには適さないとされる原料は使用しておりません。作品ご購入のお客様、体験教室等をご利用のお客様は安心して器をご使用ください。私自身も健康は損ないたくありませんので科学組成などを日々研究しております。釉薬の調合はテストテストの繰り返しです。陶器の色は焼成方法、窯の種類、土、釉薬など様々な要因が調和して出来上がっています。100のテストをして1いいのがあればいいほう。ご家庭など調合されている方も諦めずにトライしてみてください。ちなみに自己研究による解釈に基づいていますので間違っているところもあるかも知れません。が失敗した釉薬を作ってしまったと思ったものがちょっとした気づきで最高の出来になった!なんてことも最近ありました。失敗と成功は紙一重といったところなんでしょうね。
*注意…釉薬調合の際、粉末を吸い込まないよう防塵マスクを。焼成時は換気しよう

釉薬を構成する3つの要素
調合のヒント。釉薬を構成する要素としてシリカ/アルカリ/アルミナこの3要素があります。
原料が上の要素のどれなのか把握する.重複する性質を持つものも多く含まれます。
原料を買ったらとAIに聞くなり事前情報を収集し単味で焼いてみてそれから考えテストを繰り返します。
ある釉薬①=●+●+●+(●+●)
『●+●+●』の部分が釉薬を構成する基本要素でそこに『●』の色を着色するものや『●』の釉薬に
面白みを出すものを加えたりします。マット・結晶・乳濁・透明・失透などの釉調もこの混合比で変化します。
でも、世の中の面白い表情の釉薬はこの限りで作られていなかったりもするので常識外もありだと思います。
●シリカ/SiO2(珪酸分)ガラス質の素
釉薬を溶かしたいとき → 減らす
釉薬が流れすぎるとき → 増やす
釉薬に強度と艶を与える。単味で1723℃で溶解。
●アルカリ(溶かす)
釉薬を溶かしたいとき → 増やす
釉薬が流れすぎるとき → 減らす
●アルミナ(土とガラス質の間を繋ぐ)
釉薬を溶かしたいとき → 減らす
釉薬が流れすぎるとき → 増やす
貫入が多いとき → 増やす
調合比 20~30%ぐらいでマット状に
●福島長石(カリ長石)
溶解温度が高く、単味での焼成では解け方が不完全で透明感があまりない。ペグマタイト長石に分類(純度が高い長石)。*他に珪石の混じりけのあるアプライト長石(珪長石)ど呼ばれる分類もある。
●釜戸長石(ソーダ長石)
福島長石に比べ融解温度が高い。明るい色の釉薬を作るにはソーダ長石は向いていると思うが、反面貫入が入りやすくなり表面が柔らかく傷もつきやすくなる。
●平津長石(ソーダ長石)
ナトリウム分が多く1,200℃以下からと他の長石に比べよく溶けトロっとした感じに。また、透明度は高い、アプライト長石。うちの窯はOFなので厳しいですが志野釉に使われることも。*溶解度=カリ長石<ソーダ長石
●大平長石(砂婆/藻珪・カリ長石)
風化花崗岩。珪石に近い長石で砂が入っているような感じ。黄瀬戸釉などの長石としてあう。
●三雲長石(ソーダ長石)
別名山丈長石。鉄分を少し含む。前買って送られてきたらかなりゴツゴツでうちの設備では粉砕しきれなかった・・・
●珪石・珪砂
シリカつまりガラス質99%を主成分とする。増やしていくと乳濁化する。また、貫入防止効果も。単味だと殆ど溶けない。
●●天草陶石
アルミナの性質も持つ原料で磁土の元みたいなもの。アルミナの作用によりマット、白濁感も出る。単味での焼成では白色に焼け生地への定着もいい。素焼き用の化粧土としても使用可。天草陶石を使った焼き物としては有田焼が有名。
●合成藁灰
シリカつまりガラス質を主成分とする。また、珪石に近い性質がある。長石にも似た性質をもつが長石よりも溶け難い。溶解温度が非常に高く単味での焼成ではあまり溶けないものの少しガラス化もする。生地への定着は調合比(70%以上)が上げると釉切れを起こしやすくなる。リン酸分が多いため20~40%で乳濁化。
●天然モミ灰
80%前後のシリカ分を含む。藁灰と似た性質だが比べると溶け難い。単味では殆ど溶けない。黒っぽい色をしている灰。白濁して溶ける卯の斑釉が黒く見えるのはこのため。黒色の釉薬の上に塗り重ねると朝鮮唐津風に。
●ペタライト(リチウム長石)
耐熱食器に。カリ長石。土や釉薬に混ぜて使用すると膨張係数が抑えられる。直火にかけて使う食器はもちろんコレが入っている。明るい色を強調する作用も確認されたが釉縮みの原因にもなる。10%ぐらいまでか。
●●硼酸(フリット)*TOXIC
シリカやアルカリのような溶解剤の働きをする。貫入を抑え艶を促進。幅広い焼成温度帯で溶ける。鉛の代用としても使えそう。多量に使用すると発泡することも。市販の釉薬によく配合されてそう。
●霞石閃長石(ネフェリン長石)
ソーダ長石の一種。カナダ産。
●合成土灰
カルシウムを主成分とする。多少の鉄分あり。単味での焼成は溶けているが粘り気がなく不安定で艶もない。
●天然樫灰
鉄分量小。雑味が少なく澄んだ色に溶ける。標準調合比30%ぐらいか。
●天然松灰(深みを出し淡色に)
炭酸カルシウムを主成分とする。また、アルミナ分も若干含まれる。天然の鉄分(2~3%)などの雑味を多く含む。単味での焼成は雑味である鉄分の影響により若干色味が出る。調合比が増すにつれてマット感が。標準調合比50%ぐらいか。
●天然栗皮灰
鉄分量小(約1%)。雑味が少ないので淡くすっきりした釉調に。ゆえに、織部、青磁などに適しているといわれる。単味でも釉になるが安定性がない。標準調合比30%ぐらいか。
●天然橡灰
雑味成分多。若干、乳濁しマット感あり。
●天然土灰
土灰とは土の灰という意味ではない。雑多な樹木の灰という意味である。単味でも釉になるが安定性がない。調合比50%ぐらいが安定値でそれ以上だと流れやすくなる。鉄分は2~3%。
●天然イス灰
九州南部で採れるイスの木の灰。単味でも釉になるが安定性がない。すっきりした印象の釉に。透明の薬などに。鉄分は少なめ(約1%)。釉が流れにくいので染付けなどに向く。
●天然樫灰
単味では溶けにくい。一般的に硬い木の灰はは単味では溶け難いとされる。若干結晶を伴うのでそば釉の灰としても良さそう。鉄分は2~3%ぐらい。
●籾灰
珪酸分を多く含み、乳濁釉しやすい。籾や糠の灰は草を燃やした灰なので粉末や釉薬のときは黒く見えるが焼成すると白くなる。あなたが通っている教室とかで黒い色をした釉薬なのに白く焼きあがる場合はこの灰が使用されてるかも。
●唐松灰
10%弱の鉄分を含有している様子。単味で焼成するとかなり濃い色調になる。単味でも使用可。
●中仙道灰
10%弱の鉄分を含有している様子。単味で焼成するとかなり濃い色調に。単味でも使用可。
●美濃路灰
単味では溶けない。
●檜灰
単味では溶けない。
●天然ナラ灰
単味では溶けない。鉄分は少なめ。
●炭酸バリウム *TOXIC
溶解力が強く、またアルミナ分も含まれる。量が多くなると気泡が入りやすいが酸化金属などと激しく反応する。単味での焼成では溶けるがガラスのような艶は見られない。釉薬に粘りも加えるので貫入防止効果もある。織部釉に混ぜると鮮やかな青緑に。劇毒物のため食器として使うには配合比15%程度までとされている。また、バリウムマット釉は適切に溶融できているか自分で判断できな方は食器利用は控えた方がいい。現在では取り扱いも厳しく炭酸ストロンチウムへの代用が求められる。
●マグネサイト(白く溶かす)
炭酸マグネシウムを主成分とする。融解温度が高いので単味ではほとんど溶けない。結晶作用により釉薬をマット(5%以上)、乳濁化させる。貫入防止効果あり。添加量が多すぎると白い斑点が出る。
●炭酸ストロンチウム
一般的に辰砂、青磁などにキレイな色を出すために使用される。炭酸バリウムの代用にも使えるが少し効果が落ちる。代用の場合は1.3倍ぐらいか。
●●タルク
マグネシウム・塩化マグネシウム分(ケイ酸塩)を多く含む。マグネシアマットなどに。貫入防止効果あり。
●炭酸リチウム*TOXIC
塩基成分の溶解剤。トルコ青釉などに。よく分からないがオール電化対応の土鍋などはコレが入っているのかな?要研究。
●ドロマイト
釉薬の溶解剤(Flux)。マグネシウム・カルシウム(石灰)・炭酸塩を主な構成要素とする。貫入防止効果あり。結晶性マットなどに。例)マグネシア成分がCoOを結晶をともなったラベンダーマットに変化させる。
●硼砂(Borax)
ナトリウムと硼酸の化合物。溶解温度878℃。
●白石灰
釉薬の溶解剤として代表的なもの。鼠石灰などもあるが粉末の時の色が違うだけでほとんど一緒?
●日本陶料カオリン
磁土に近い性質。単味焼成では粘土に近い性質のため固まるが溶ける様子はない。マット感を加えたいときにも。添加し過ぎると釉が縮む。化粧土で使う場合、長石を微量加えると馴染みが〇。
●ニュージーランドカオリン
他のカオリンに比べ雪のような白さに。
●広東カオリン
少し青みがかった白色に
●蛙目粘土
鉄分などの雑味成分あり。珪石粒を含むので少しザラザラした質感に。可塑性に優れ釉薬や化粧土の食い付きを良くし沈殿防止効果もある。光が当たると蛙の目に見えたことからこの名前がついた。
●大道土
萩焼に使われるざっくりした陶土。細かい砂分と鉄分を含む。
●木節粘土
枯れた草木などの有機物を多く含む。可塑性が非常に優れ粘りがある。また乾燥強度が高い。
着色剤
天然灰などに若干の鉄分など含まれ色が着きますが
意図的に色を入れたいとき下の着色金属類を使用することがあります。
*酸化金属類は釉を溶けやすくします。流れすぎに注意。
●酸化鉄・紅柄(黄・黒・青磁)
酸化第二鉄を主成分とする。鉄絵の下絵具にも使用される。高級品だと鉄分の含有量が多い?一般的に鉄分の量が増えると釉が溶けやすくなる。ex)黄瀬戸2~4%/飴釉5~7%/黒釉10%~
●中国黄土
含鉄土石類で鉄分の多い(約19~25%)天然の粘土。アルミナ分も含む。紅柄よりも鉄分は少ない。落ち着いた色調の鉄釉や、生素地用の化粧土、絵の具としても使用。
●黒顔料
金属顔料を溶かし発色させてから粉砕させたもの。安定した色味が得られる。
●鬼板
原石は鬼のように硬いというところから鬼板とついたとか?含鉄土石類で鉄分20~30%を含む。鉄絵の具としても使用。織部の鉄絵の部分とかはコレが多いのではないでしょうか?素地土に数%混ぜて使用しても面白いかも。
●来待石
島根県で採取される含鉄土石。鉄分約6%を含む。ガラス質で単味で釉になる。1,280℃
●珪酸鉄
紅柄と珪石を1:3で混合し焼成された顔料。
●酸化銅(青/緑/黒/赤/紫)*TOXIC
黒色の粉末。焼成時に揮発性あり。焼成時近くに酸化銅を使用したものを置くと色移りすることがある。タンバン(黄瀬戸の緑色のとこ)にも使われる。この場合、少し灰と混ぜるとなじみがよい。ex)0.5~10% 3~5%で織部
●炭酸銅 *TOXIC
緑色の粉末。酸化銅の代わりに使用する場合は1.4倍で計算すること。添加量が増えてもあまり黒っぽくなならない。
●硫酸銅
鮮やかな青色をしている。黄瀬戸のタンバンに使われる。抜けタンバン(器の反対側に銅が移る)も出やすいらしいけど、高価なため殆ど使用せず酸化銅を代用。
●二酸化マンガン*TOXIC
鉄釉などに。結構好きです。アトリエに常備の海碧呉須に少量混ぜると藍色に。
●酸化クロム*TOXIC
緑色の着色剤。他、赤、黒などにも発色。酸化錫と調合すると赤やピンクに。また、発色を濃くするために使用する。
●加茂川石
約15%の鉄分/マンガンを含む珪石質の含鉄土石。単味でもよく溶ける。
●酸化コバルト(青系)*TOXIC
発色性が強く安定した金属。還元焼成の方がより青みが強くなる。約1%の添加で海鼠釉ほどの発色に。非常に高価な原料だが鉄釉を作るときなどに若干添加すると深みがでる。ex)0.1%~
●呉須
酸化コバルトを主成分とした染め付けの青顔料。海碧呉須、古代呉須など地方等により様々な種類がある。お茶で粉をあてると呉須よく伸びる。(カテキンが効くらしい)
●酸化ルチール
黄色い粉末。少し結晶を伴う材料か?非常に変化があり渋い。
●黒浜
砂鉄のこと。花崗岩が風化した後に残った砂鉄分で約80%の鉄分を含む。鉄釉やチタン結晶釉などに。
●酸化ニッケル*TOXIC
灰色、青、赤紫、ヒワ色、黒色などに発色。不安定な発色を示し、調合により色々な発色をします。
●益子赤土(益子赤粉)
益子で鉄釉や黒化粧として使われる含鉄土石。珪酸、酸化鉄(約6%)に微量のリン酸を含む。来待石に性質が似ている。SK9(1280℃)で柿釉に。
添加剤
釉薬に結晶作用など変化を出す
●珪酸ジルコニウム(白くなる)
ジルコンとも呼ばれる。強力な乳濁作用あり。融解温度高い。安定した白さ(12.5%~)を得ることができるが添加しすぎると釉調が単調になる傾向がある。よくペンキのような・・・と形容されてる。単味での焼成では殆ど溶けない。
●シリコンカーバイト
釉薬を発泡させる作用がある。Lucie lieの溶岩釉など。添加量が比較的少なめの方が発砲が大きいような気がする。
●酸化錫
乳濁作用あり。うっすらピンク、還元作用あるかも?2~7%ぐらいで貫入防止効果もある。
●●亜鉛華
強力な溶解作用がありアルカリ土類に似たような働き。明るい発色をする。20%ぐらいの添加で大きな結晶ができる亜鉛結晶釉に。徐冷が結晶を育てるポイント。多量に添加するとピンホールを発生させる。RFでは金属の各性質を減少させるため使用するべきではない。
●蛍石
強力な乳濁作用のある蛍石は900℃ぐらいから溶けだし高温になるとフッ素とシリカが反応し発泡すると言われている。
●●第三リン酸カルシウム(合成骨灰)
骨灰の合成版。溶解剤、乳濁剤として。単味では殆ど溶けない。
●酸化ルチール
金鉱石と呼ばれる鉄分を含有する天然のチタン鉱物。非常に強い結晶作用が特徴。鉄分の影響により黄味がかる。融解温度を下げる効果も。そば釉で白斑点、縞々を出すときにも。
●酸化チタン
強力で安定した結晶作用がある。パール状な変化のあるマット感を出したいときに。過度に添加すると融点が下がり流れやすくなる。
●●骨灰
牛などの動物の骨を焼いたもの。2%~で乳濁化。リン酸カルシウムの結晶が生じる。単味では殆ど溶けない。失透釉、鉄赤、まだら、縞々。
その他
●3号石灰透明釉
日本陶料さんの日本でもっとも基礎釉として使われていると思われる透明釉。SK7(1230℃)で溶け非常に安定した釉薬。これに着色金属などを加えるだけで気軽に色釉など作ることができる。
●カリ石鹸
石膏型を作るときに使用する離型剤。
●シャモット
素焼きを粉砕したもの。耐火度を上げたいときや大物作陶のときの骨材として陶土に混ぜて使用することがある。乾燥時のヒビ割れ防止にも。
●トチ渋
どんぐりのヘタを水で暫く漬け込んだもの。織部釉の酸化皮膜除去に。貫入に黒ずみが入り趣が出ます。
●撥水剤
釉抜きに。揮発性が高い。素焼き生地にも釉掛けを行ったあとにも使用可。一度塗るとその部分には釉が乗らなくなるので注意。誤ってしまった場合は、素焼きであればサンドペーパーで擦ると若干は取り除くことができる。使用した筆が傷みやすいので専用の筆を用意し、食器用洗剤か灯油で使用後の筆をよく洗うこと。
●ラテックス(陶画のり)
簡単に言うとゴムの液体。臭い。撥水剤と違い釉掛け後にはがすことができるので2重掛けなどに向く。木工ボンドがポリッと剥がれるようなイメージ。上の撥水剤と同様に使用した筆が傷みやすいので専用の筆を用意し、食器用洗剤か灯油で使用後の筆をよく洗うこと。
●にがり(塩化マグネシウム)
沈殿防止剤として。長石多めの釉薬だと効果が薄い?
●C.M.C(セロゲン)
合成のり。釉薬や絵の具の接着剤として。釉薬ののりが悪いときなどに。釉はがれの防止には1Lの水に1~2%程度セロゲンを入れ、3日くらい放置しその溶液を5%前後釉薬に加える。
●セラムボンド
素焼き製品の接着剤。粉末に少しづつ水を加えペースト状にし使用する。接着面の片方に塗り圧着。
●水酸化アルミニウム(アルミナ粉)
焼成具である棚板に塗ってあるあの白いもの。融点が2050℃と非常に火に溶け難い性質を持つ。コレに蛙目粘土、木節粘土、カオリンなどを少し混ぜ水に溶いて使用する。作品が棚板と溶着してしまうのを防ぐ。水アルミナは吸着性が高いので棚板の裏側に塗ると良い(剥離して器に落下しずらいため)。
Health & Safety
木灰やリチウムのようなアルカリ性の強い物質を釉中に含む場合はゴム手袋などで手を保護し撹拌すること。ホタル石やマンガンは焼成中、有毒ガスを発生するのでよく換気をすること。シリカを含む粉末状の原料を取り扱うときは防塵マスクの着用が望ましい。また、工房内は定期的な雑巾がけを。鉛やバリウムが使用された釉薬は食品中の酸性分が食器表面を分解し重金属部に達するため食器類には適さない場合があります。そのため十分な比率のシリカとアルミナ分を含んだ釉薬で適正焼成することにより耐酸性を得てております。従来、鉛は面白味のある釉調が低火度焼成で得られたため大量生産品や海外生産などの安い食器に使われることがありました。しかしながら、鉛の人体に対する有毒性が広く認識されるようになってから多くの陶芸家は鉛の使用をやめ硼酸などの代用品を使うようになっております。なお、当Studioでは鉛は使用しておりません。器は楽しく安全に作って使って健康第一!
*Highly toxic
・鉛・バリウム・赤/オレンジ/黄色などの顔料・三酸化アンチモン・五酸化バナジウム・酸化ニッケル・酸化クローム・マンガン
*Toxic
・酸化コバルト・銅・リチウム・硼酸・亜鉛